つい、『○○したら△△買ってあげる!』と言ってしまうこと、ありませんか?
「おもちゃを片付けたら、おやつをあげるよ」
「宿題を終わらせたらゲームしていいよ」
「テストで100点取ったら好きなもの買ってあげる」
無意識に言ってしまったり、やむを得ない状況で仕方なく使ってしまったりと、一度はあるのではないでしょうか。私もその一人です。
働きながら3人の子どもを育ててきた私ですが、仕事・家事・育児に追われ、バタバタな日々を送ってきました。その中でうまく生活をしていく方法の一つとして考えたことが、結局モノで釣っていた!ということもあります。
今回は子どもを『ご褒美(モノ)で釣る』ことに関して、ネット上の意見を参考にしながら考えていきたいと思います。
「ご褒美をあげるのはダメなこと?どう付き合えばいいの?」と悩んでいる方へ。この記事がヒントになれば嬉しいです。
子どもをご褒美(モノ)で釣るのは本当にダメ?
「ご褒美(モノ)で釣るのは良くない?」という疑問について、様々な意見があります。ここではネット上で見られた意見をまとめてみました。
様々な意見に耳を傾けながら、自分や自分の子どもたちはどうかな?と当てはめて考えてみましょう。
【デメリット】やる気が育たない?|否定派

- 自らから「やりたい!」と思う気持ちが育たない
→ 報酬がないと行動しなくなり、興味ややる気が自発的に生まれにくくなる。 - 物への執着が強くなる
→ ご褒美を目的に行動するようになり、物質的なものばかり求めるようになる。 - 継続的な効果が期待できない
→ 報酬がもらえないと行動しなくなり、一時的な効果しか得られない可能性がある。 - 要求がエスカレートする
→ 最初は小さなご褒美でも満足していたのに、次第にもっと大きな報酬を求めるようになる。 - 親子関係が取引的になる
→ 「○○したら△△をあげる」という形が習慣化すると、親子の信頼関係が薄れ、愛情よりも条件で動く関係になってしまう。 - 報酬がないとルールやマナーを守らなくなる
→ 本来、道徳的にすべき行動(片付け、挨拶、勉強など)を、ご褒美なしではやらなくなる。

子どもをご褒美(モノ)で釣ることに対して、さまざまなリスクが指摘されています。これらの意見を見ていると、やっぱりやってはいけないことなんだと感じますね。
【メリット】やる気を引き出せる?|肯定派

- 即効性がある
→ ご褒美を提示すると、すぐに行動を起こしやすくなる。 - 動機づけのきっかけになる
→ 最初はご褒美が目的でも、続けるうちに楽しさを感じ、自発的に取り組むようになることがある。 - 成功体験を積みやすい
→ 「○○をしたらご褒美がもらえた!」という経験が自信につながり、やる気が出る。 - 頑張ることの楽しさを学べる
→ 「努力すると良いことがある」と理解し、粘り強く挑戦する姿勢が身につく。 - ルールや習慣を定着させる手助けになる
→ 勉強や片付けなど、最初は嫌がることでも、報酬を与えることで習慣化しやすい。 - 子供が目標を意識しやすくなる
→ 「あと〇回やったらご褒美がもらえる!」と分かることで、目標を達成しようとする意欲が生まれる。 - 適切に使えば悪影響は少ない
→ いつもではなく、たまに使う・ご褒美の与え方を工夫することで、内発的動機づけを損なわずに済む。

子どもの成長をサポートする手段として有効な場面もあるという考え方ですね。でも言い方や頻度など親がよく考える必要がありますよね。
私の場合
私もこれまで3人の子どもの子育てをしてくるなかで、子どもを“ご褒美(モノ)で釣る”ことに心当たりは山ほどあります。
言うことを聞いて欲しいとき、早く行動して欲しとき、頑張って欲しいとき…
子どものためと思うこともありますが、親の都合のときもあります。
私がこれまで“ご褒美(モノ)で釣った”事例をお伝えしたいと思います。
1つは完全に良くないパターンです。今だったらこうしたな~という改善策も含めお伝えします。2つ目は考え方によると思います。現在も続いている子どもとの約束ごとになっています。
皆さんは私の事例からどう感じるでしょうか。一緒に考えてみてください。
ジュースで釣った結果…どうなった?
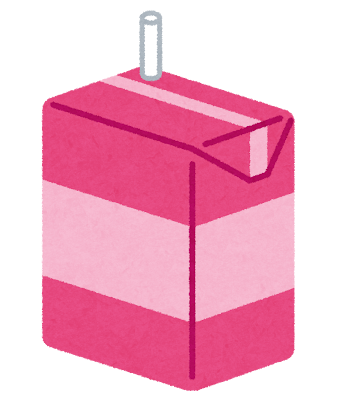
保育園のお迎えの際、なかなか車に乗ろうとしない娘に対し、
「車に乗ったら、アンパンマンジュースあげるよ!」と言っていました。
当時アンパンマンのパックのジュースが大好きだった娘。保育園のお迎えのあとは、長女の習い事のお迎えに、次男の児童クラブのお迎えと何か所もはしごをしていた私にとってアンパンマンのジュースは救世主でした。
しばらくすると保育園の身体測定後に先生から声をかけられました。

体重が急に増えてきていますね、心当たりありますか?

すごくあります…
私は子どもが大好きだったアンパンマンジュースを利用していました。そのため、体重が急激に増え、見るからにパンパンになっていました。
以後アンパンマンジュースの作戦は中止となりました。次第にアンパンマンジュースから車の中のテレビへ興味が移行し、すぐ乗るようになり助かりました。
- ご褒美を続けると習慣化し、やめるのが難しくなる
- 代わりに「言い方」を工夫することでスムーズに誘導できる
モノ以外にしてみる
今であれば、他の楽しみを探してみます。
子どもを誘導する効果は薄れるかもしれませんが、子どもへの影響を考えないといけませんね。
言い方を考えてみる
「車に乗ったらアンパンマンジュースあげるよ!」というのは、「乗らないとあげないよ!」と同じですよね。つまりは乗ることを条件として提示していますね。
今であれば、こう言い換えます。
「車に乗ったらアンパンマンジュース飲もうか!」
→条件ではなく、あくまで誘っている。
大差がないように思いますが、『あげるよ!』は条件付き、親が与える印象が強いですが、『飲もうか!』は楽しみ、共同行動でポジティブ、何より自然な伝え方ですよね。
ゲームで釣る
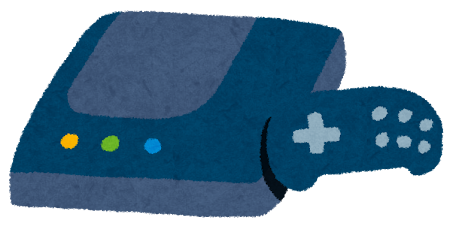
娘が小学生になり、ピアノを習い始めました。しかし週に一度しか練習をしません。しかも少し弾いてすぐに終わる…。
そんな娘に『ピアノの練習したらゲームの時間増やすよ!』と言いました。
効き目は抜群です。毎日ゲームの時間を増やして欲しい娘は、毎日練習をしました。しかも条件には30分練習しないとダメというルールがあったので、めきめきと上達をし、初級コースからコースも変更になりました。
しばらくすると「今日はゲームできないから練習もしない~」と言うようになりました。こんなことを言うのは予想できますよね…。
しかしピアノが上達した娘は、ピアノを習っていない姉や兄に「こんな曲も弾けるようになったの?すごいね」と言われることが嬉しいようで、ピアノの習い事も「やめたくない!楽しいよ!」と言っています。上達したことが今の習い事へのモチベーションになっているようです。

また最近娘にピアノの練習しないとゲームできないってどう?と聞くと「努力しないとゲームしちゃいけないってことでしょ?」と自分なりに解釈していたようでした。
小学生の高学年になり、物事をちゃんと考えられるようになってくると、“ご褒美(モノ)で釣る”ことをきっかけにすることは悪いことでもないのだと感じました。
まとめ
子どもを「ご褒美(モノ)で釣る」ことについて、否定的な意見もあれば、うまく活用すれば効果的だという意見もあります。大切なのは、ご褒美の使い方とバランスだと思います。
私自身の経験を振り返ってみても、ご褒美が必ずしも悪いわけではなく、子どものモチベーションを高めるきっかけになることもあります。しかし、常にモノで釣るのではなく、声かけの仕方やご褒美の内容を工夫することが大切だと感じました。
- 「〇〇したら△△」ではなく、ポジティブな声かけに変える
- モノだけでなく「時間」「経験」などのご褒美も活用する
- 最終的には「自分のためにやる」ように導く
子どもにとって「やりたくないこと」を続けることは簡単ではありません。ご褒美を活用することで、小さな成功体験を積み重ね、やる気や自信につなげることもできます。
親としては、子どもの気持ちや成長を見ながら、上手にご褒美を取り入れ、最終的には「自分のために頑張る」ことができるようサポートしていきたいですね。

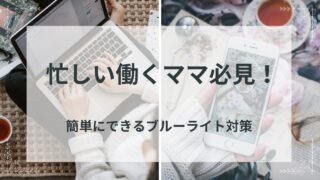
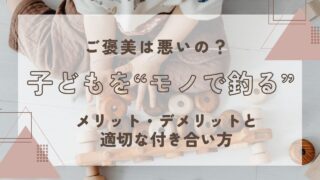
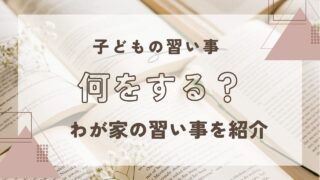
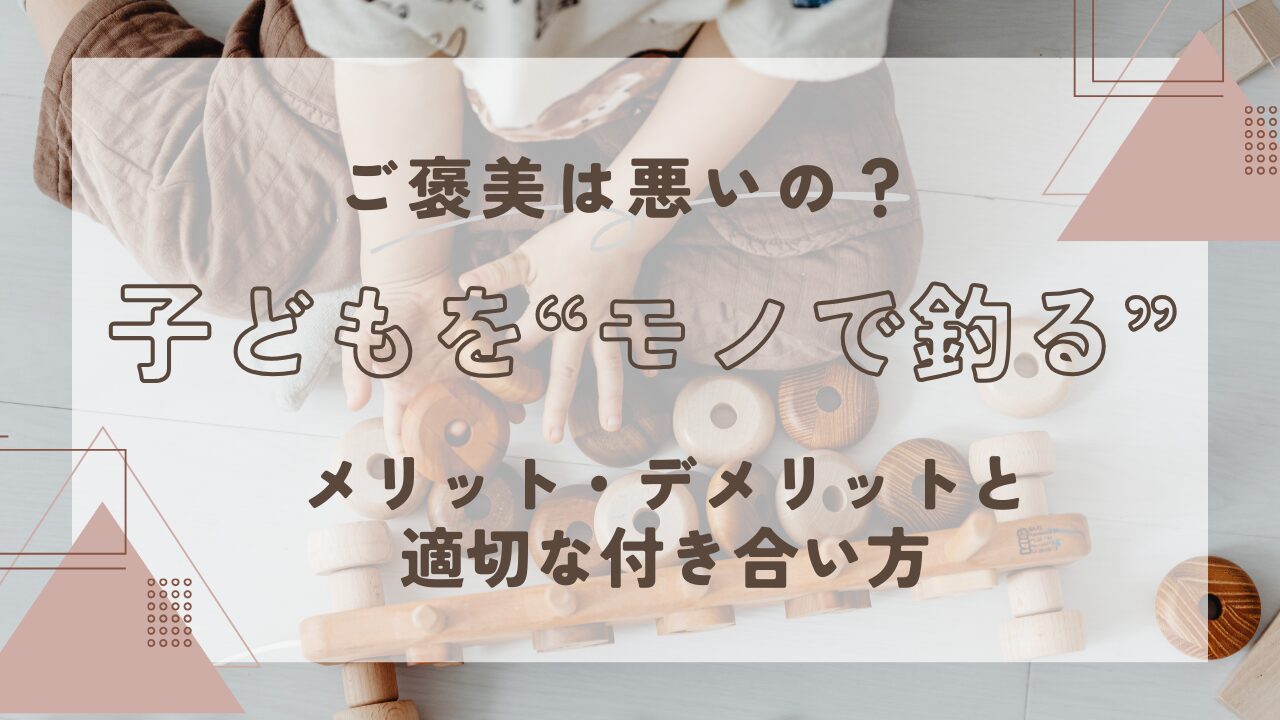
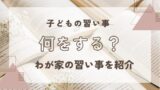
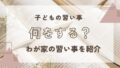
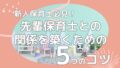
コメント